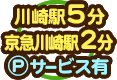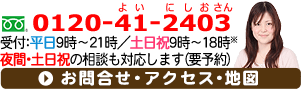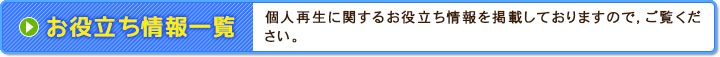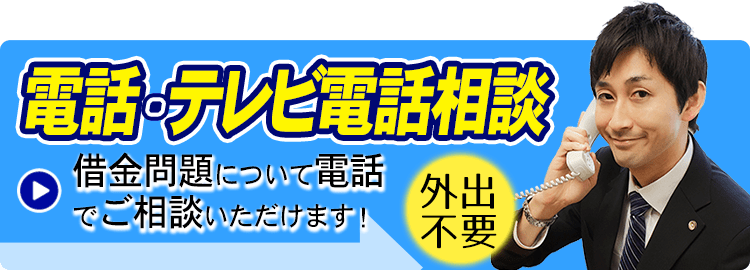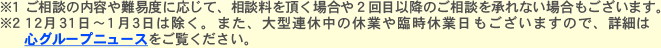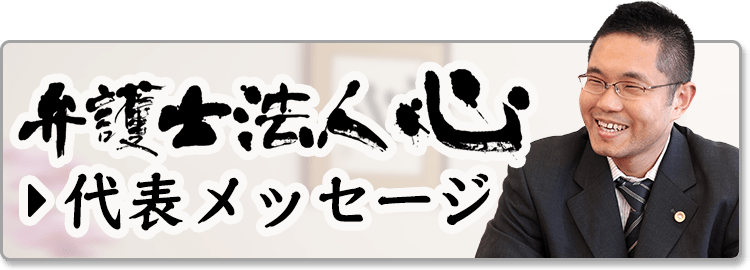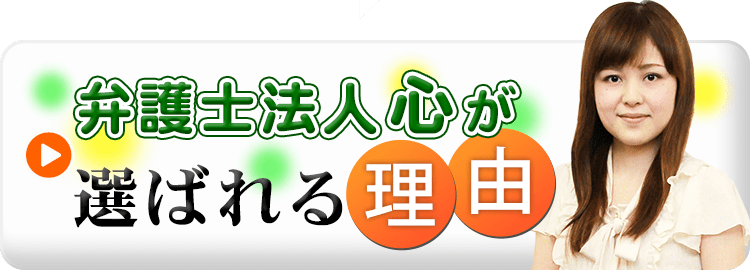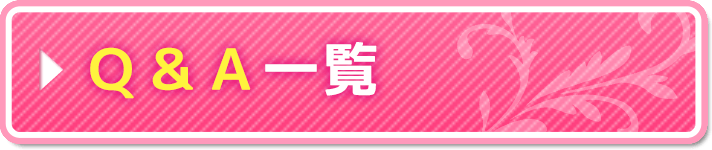「手続開始後の問題点」に関するQ&A
個人再生をしたとき債権者から反対されることはありますか?
1 小規模個人再生においては債権者が反対することはある
結論から申し上げますと、小規模個人再生の場合、債権者が再生計画案の認可に反対する可能性があります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがありますが、実務においては、小規模個人再生が選択されることが多いです。
小規模個人再生には債権者の意見を聴く手続きがあり、一定の基準を上回る債権者の反対があると、再生計画が認可されないことになります。
以下、小規模個人再生における債権者の意見回答、および実務における対応について説明します。
2 小規模個人再生における債権者の意見回答
小規模個人再生は、債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年間で分割返済できるようにする制度です。
手続きにおいては、再生計画案を債権者に提示し、一定の基準を超える不同意意見が出た場合には、再生計画案が認可されません。
具体的には、以下の2つのいずれかの場合、再生手続廃止の決定がなされます。
①債権者の過半数が不同意意見を出していること
②反対する債権者の債権額が総債権額の2分の1を超えていること
債権者1社で債権額の半分以上を占めるケースにおいては、その1社が不同意意見を回答することで、再生計画案が認可されないことになります。
3 実務における対応
小規模個人再生の実務においては、債権者からの不同意意見によって手続きが廃止されることを回避するために、以下のような対応をとることがあります。
まず、個人再生の準備段階で、債権者の構成を確認します。
不同意意見を出すか否かは債権者の方針次第であり、中には不同意意見を積極的に出す債権者も存在します。
そのような債権者が多くの債権を有している場合には、予め小規模個人再生以外の方法(給与所得者等個人再生や自己破産)を検討します。
給与所得者等再生であれば、債権者の不同意により手続きを廃止にするという制度自体がありません。
ただし、給与所得者等再生を利用するためは、原則として給与所得者であること、収入の変動が小さいこと、可処分所得基準を満たすことという条件を満たす必要があります。
特に、可処分所得基準は、1年間あたりの手取り収入額から、政令で定める最低生活費を控除した額の2年分を返済しなければならないというルールですので、ある程度収入がある場合には返済額があまり下がらないこともあり得ます。
個人再生をした後、現在借りている家の契約の更新をしたり、新たに家を借りることができますか? 個人再生を自分で申し立てることはできますか?