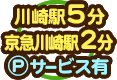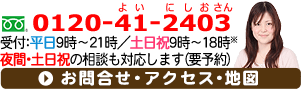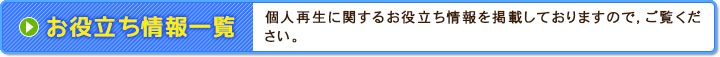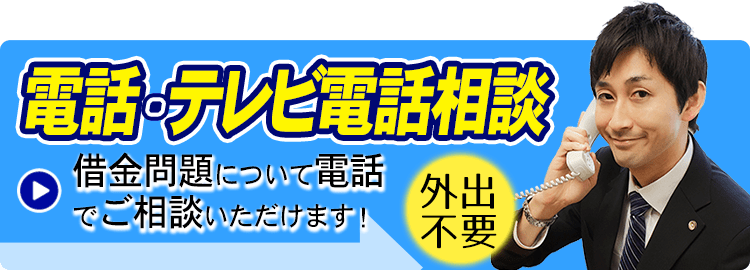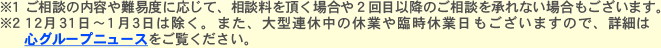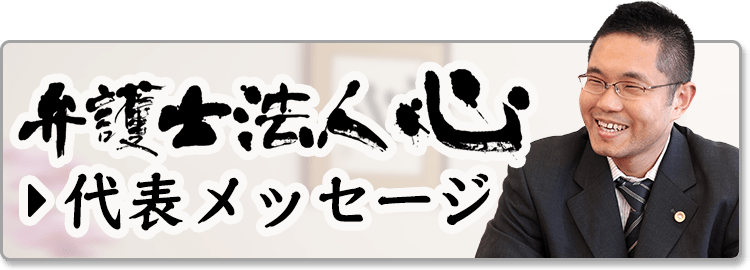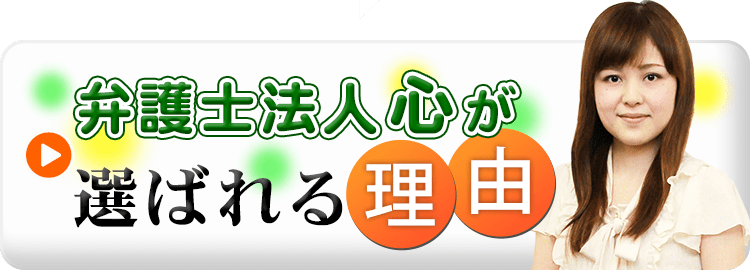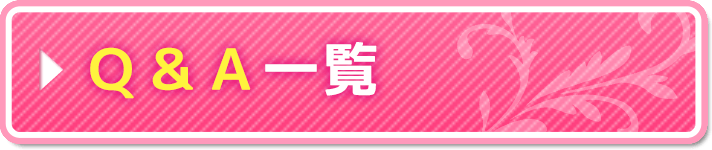「個人再生の手続き」に関するQ&A
個人再生を自分で申し立てることはできますか?
1 法律上は自分でも個人再生は可能
結論としては、法律上は、債務者の方が自分で個人再生を申し立てることは可能です。
弁護士を代理人とすることが義務付けられているわけではありません。
ただし、個人再生は債務整理の中でも複雑な類型のものです。
申立ての準備の際には専門知識に基づく多くの書類作成、資料収集が必要とされますし、手続き開始後も、裁判所や再生委員との的確なやり取りが要求されます。
現実的には、弁護士を代理とせずに個人再生をするのは、かなりの困難といえるでしょう。
また、事案の内容や、裁判所の運営方針によっては、弁護士を代理人としている場合、再生委員が選任されず、費用や対応負担を抑えられることがあります。
以下、詳しく説明します。
2 個人再生の準備と手続きは複雑
個人再生の申立ての際には、多数の書類の作成や、財産・身分に関する資料の収集をする必要があります。
例えば、申立書のほか、債権者一覧表、債務の詳細、数か月分の家計表、給与明細、源泉徴収票、課税証明書、退職金見込額計算書、過去数年分の預貯金通帳の写し、不動産の査定書、保険の解約返戻金計算書、住民票などが挙げられます。
書類に不備がある場合、補正を求められますが、このときの対応がしっかりとできないと、再生手続きが開始されないことがあります。
申立て後、再生手続きが開始されたら、履行テスト、清算価値の算定、再生計画案の提出等が行われますので、随時必要な資料の提出や、裁判所・再生委員からの指示への対応を行います。
これらの対応に不備があると、再生手続きが進まないだけでなく、場合によっては個人再生ができなくなることもあります。
3 弁護士に依頼すると再生委員が選任されないこともある
個人再生においては、再生委員が選任されるか否かも、手続きの進行や費用に大きく影響します。
再生委員とは、裁判所が選任する、個人再生手続きの管理監督者のことです。
一般的には、弁護士を代理人とせずに申立てた場合、再生委員が選任されやすい傾向にあります。
この場合、再生委員との面談などに応じる必要があるほか、再生委員に対し15万円程度の報酬を納める必要があります。
弁護士が代理人になっている場合、裁判所が手続きの信頼性を担保できると判断し、再生委員を選任しないこともあります。
なお、弁護士が代理人であっても、必ず再生委員を選任する裁判所もありますので、「自分の場合は再生委員が選任される可能性があるのか」という点については、事前に弁護士等に相談されることをおすすめいたします。
個人再生をしたとき債権者から反対されることはありますか? 個人再生をする場合、家計簿をいつまで付けなければいけないのですか?