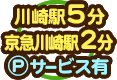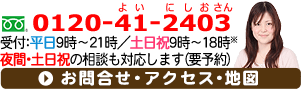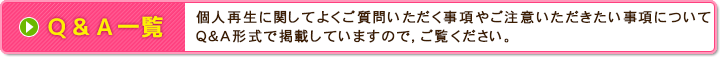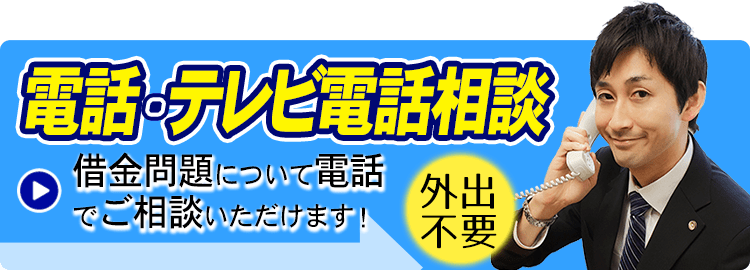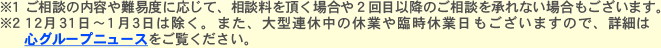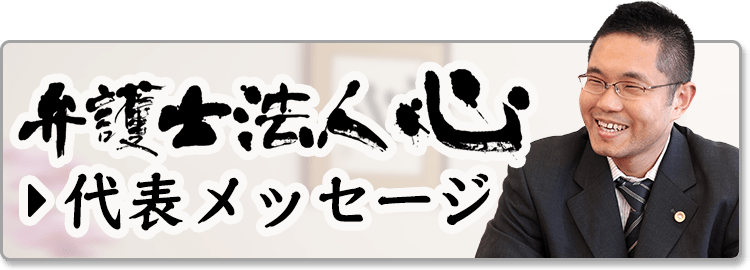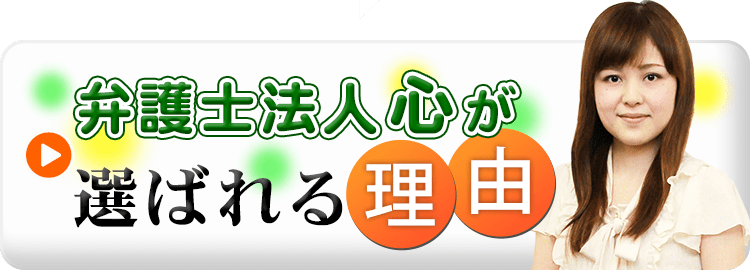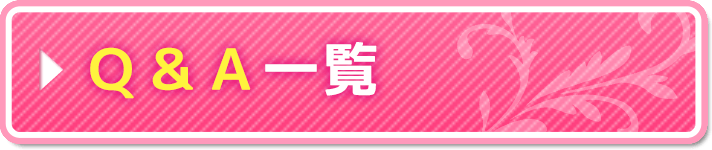「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報
個人再生におけるリフォームローンの扱い
1 不動産に担保が設定されているかどうか
個人再生において、リフォームローンはどのように扱われるのでしょうか。
基本的には、住宅に抵当権を設定しているかどうかで、その扱いは大きく変わります。
2 不動産に担保を設定している場合
リフォームローンが不動産に抵当権を設定している場合、抵当権は、原則、個人再生の影響を受けないので、競売等の手続が進められ、不動産を失うことになります。
しかし、個人再生には、再生計画に住宅資金特別条項を定め、住宅ローンだけ特別扱いをして、抵当権の実行を防ぐことができます。
そして、住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付には、住宅ローンだけでなく、住宅の改良のための資金の貸付であるリフォームローンも含まれています。
そのため、その他の要件(不動産を居住の用に供していること、自らが所有していること、他の担保権がないこと等)をみたせば、不動産を担保にしているリフォームローンについても、住宅資金特別条項を定めて、約定とおりの支払いを継続すること等により、抵当権の実行を避け、不動産を失わずに個人再生の手続きを進めていくことができます。
ただ、この場合には、リフォームローンの支払債務が減少することはありません。
3 不動産に担保を設定していない場合
リフォームローンが不動産に担保を設定していない場合には、他の借入れによって発生した債権と同様、再生計画に従って減額され、他の債権と同様に分割で支払っていくことになります。
仮にリフォームのためのローンだとしても担保権を設定していないのであれば、個人再生によりリフォームローンが減免されても、不動産を失うことはありません。
ただ、一般にリフォームローンは他の債権等と比べて金額が大きいことが多いです。
小規模個人再生には、債権者の頭数の半数、かつ、債権額の半額の反対がないことが必要になります。
そのため、リフォームローンの金額が大きく、債権額全体の半額を閉めるような場合には、リフォームローン債権者が反対すると小規模個人再生は廃止となってしまいます。
そのため、そのような場合には、リフォームローン債権者の意向を確認したり、債権者の反対に影響を受けずに手続きを進めることができる給与所得者等再生の手続きをとることを検討する必要があります。
住宅資金特別条項を利用できない場合 住宅ローンの巻き戻しとは